かかりつけセラピストの堂新橋(どうしんばし)です(^^)
ここ数日、知人のSNS投稿などで「パーキンソン病」
という言葉をよく耳にします。
偶然なのか。必然なのか。
気になったので、少し調べてみることにしました。
パーキンソン病は、運動指令を中継する中脳の黒質や
大脳基底核の異常によるもので、
運動機能をコントロールし、筋肉の働きを調整している
ドーパミンとアセチルコリンの拮抗バランスが崩れ
体を動かす為の指令が、脳から筋肉にうまく伝わらず、
思うように動けなく病気です。
主な症状として手足の震え(振戦)やこわばり(固縮)、
転びやすい、汗やよだれが多くなる、顔が脂ぎる、
気分の落ち込み、血行不良による冷えや浮腫み など

という、こちらの研究資料からも私たちの嗅覚とパーキンソン病は
密接に関わっていることがわかります。
では、パーキンソン病に対してアロマテラピーに期待できることは?
健康包括支援協会代表理事の軍場先生のブログでも
以前レシピが紹介されていましたが、
薬理作用から考えれば、ドーパミンの分泌を高めると言われる
d-リモネンやゲラニオールの芳香成分があります。
(特許庁の電子図書館にも掲載されているそうです)
d−リモネンを含む精油としてフランキンセンス、リトセア
ゲラニオールを含む精油としてゼラニウム、パルマローザ
他にもパーキンソン病に伴い、発症しやすくなるという認知症の予防にも
香りによる脳への刺激は大切な役割があります。
簡単な方法として、芳香器をつかって室内に香らせば、
嗅覚を伝わって香りの成分を脳に伝わり作用する、
吸い込んだ香りが肺胞を通って血液中に流れ、
全身の働きかけます。
また精油をホホバ油などの植物油に10〜20%濃度で希釈し、
震えやこわばりのある手足をマッサージしてあげることで、
緊張緩和や血流改善が期待で来ます。
それに加え、タッチング(手当て)による温もりと安心感が
更なる患者様(ご家族様)の心のケアに繋がります。
おうちでご家族がマッサージする時に大事なことは
技術ではなく、相手を想う心です。
目の前のご家族の身体の緊張がだんだん緩んで、
血行も促され、顔にポッと血色がよみがえり「気持ちいいわ〜」
という表情をされることを思い浮かべてみてください。
きっと、病院で治療を受けている時より
全身で何倍もの幸せを感じていると思いませんか。
精油を選ぶにあたっての私の考えは、
薬理作用を期待する事もちろん良いのですが、
それ以上にご本人が「心地よい、好きだ」と感じるもので
あることが重要だと思っています。
心地よさや、好きだという感情は、
体の中でそれを求めているというシグナルです。
素直にそれに従うことが一番アロマテラピーの醍醐味ではないでしょうか。
私の仕事はセラピストです。
医療者ではないので、診断も治療も出来ません。
私の出来ることはカウンセリングによって、
その人の今の状態や特性を知ること。
その人に合わせたオーダーメイドのアドバイス(指導)をすることです。
私にとってアロマテラピーの定義は、
「症状の緩和を手助けするもの」
「香りによる心の安定を得ることで、人生の質を向上するもの」
お薬のように使うものでも、治療として使うものでもありません。
しかしながら、心と体はつながっています。
香りで得た情報をもとに、心と体のバランスを整えることで、
お薬以上のパフォーマンスを発揮することもあると信じています。
アロマテラピーに関してのご質問やご相談はお気軽にご連絡ください。
今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
|
海外の一部地域では、健康とされる人が日々の予防や不調の改善を目的に 自然療法の一環としてアロマテラピーが使われています。 しかしながら日本ではアロマテラピーに用いる精油は「雑貨」扱いです。 医師法や薬事法により国家資格を持たない者の診断行為、治療行為、調剤行為などは、 厳しく規制されています。 当ブログに掲載の内容をもとにアロマテラピーを実践される場合は、 特定の疾患をお持ちの方やお薬を常用されている方などは、使用前に医師に相談の上、 必ず用法容量を守り自己責任において使用してください。 また精油の刺激性や毒性も個人差があり、体調によっても結果は異なります。 必ず、事前のパッチテストを実施を行い、 使用中も何らかの異常を感じた場合は必ず医療機関を受診ください。
メディカルアロマの実施には正しい知識と、信頼出来る品質の精油が必要です。 期待の効果や結果が得られない場合、また万が一の事故が起こった場合も、 当方では責任を持ちかねます。予め、ご了承くださいますよう、お願いします。
アロマ空間Cocoro 代表 堂新橋桂子 |
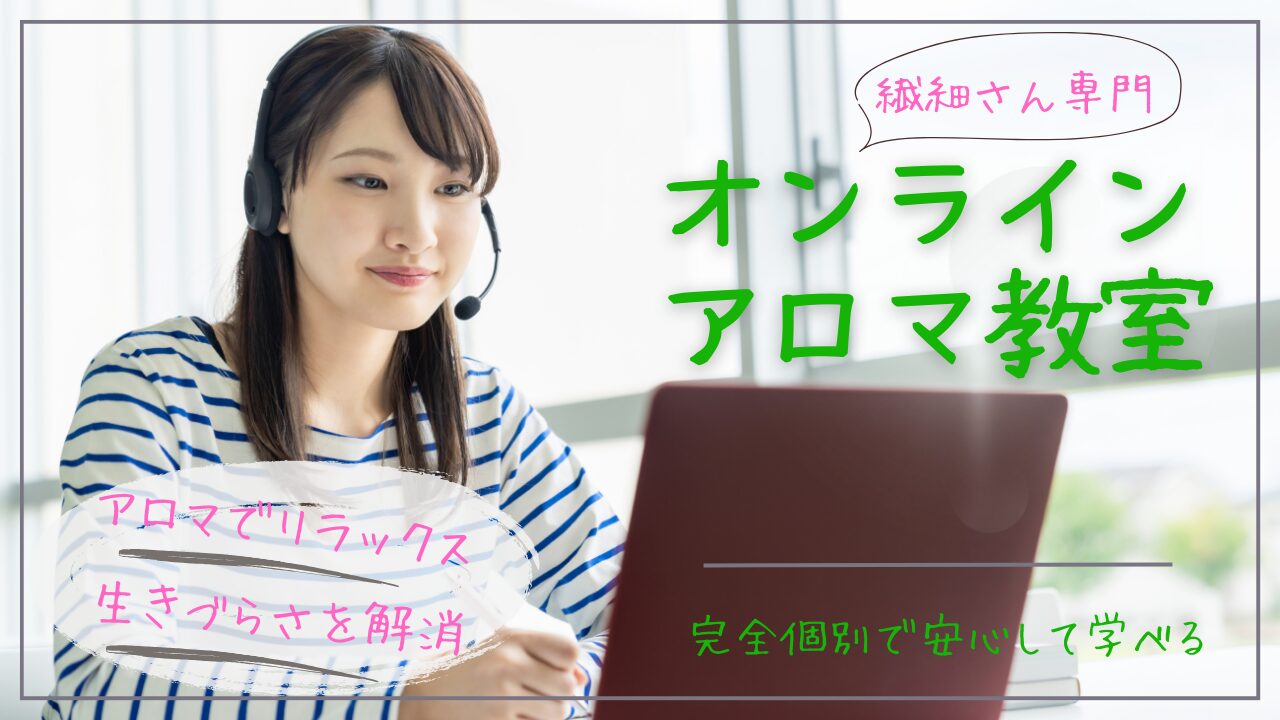



コメント